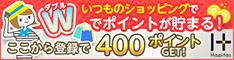英単語のgrade(等級、学年、評価、傾斜)は基礎中の基礎単語で、日本では、グレードが高い、ハイグレードといったような使われ方をしていて、この言葉がすっかり定着しています。このgradeという単語は、簡単なようで、実は意外と意味不明な用法が隠されているので、今回は、この初級レベルでありながら奥が深い英単語について調べてみました。
grade intoの意味と用法
GRE(graduate record exam、大学院進学適性試験)の過去問に、以下の問題があります。
In parts of the Arctic, the land grades into the landfast ice so ___ that you can walk off the coast and not know you are over the hidden sea.
landfast ice = 陸続きの氷原、hidden sea = 隠れた(目に見えない)海
この英文のgrades intoは、溶け込むという意味で、つまり、陸が、陸続きの氷原に溶け込んでいると訳せます。つまり、北極の一部では、陸なのか氷原なのか区別が付かないので、知らない間に下が海の氷の上を歩いているということです。
grade into ~ = 徐々に(色や形が)~に変わる、溶け込む
grade schoolの意味
grade school = elementary school (場所によっては小中高だったり、私立と公立でも違いがあるようです)、elementary schoolという言葉は、アメリカにいた時は、あまり耳にはしませんでした。大学の講師は、好んでgrade school、grammar schoolを使う傾向が強かったように思います。小学校を意味する英単語には、この他にもprimary schoolという語があります。小学生は、grade schoolerが最もよく、周りのアメリカ人達によって使われていました。
中学校は、middle schoolかjunior high schoolですが、これも、国や地域によって、かなり意味合いが違ってきますが、全く一緒と思って問題ありません。面白いのは、middle schoolにしてもjunior high schoolにしても、一部の学区では、日本でいうところの小学6年生~中学2年生までを中学生と呼んでいて、中学3年生~高校3年生を高校生と呼んでいることです。日本と全く同じグレードシステムを導入している州や地域もありますが、この辺のところは、時代や州や学区によって大きく異なってくるのが、アメリカと日本の大きな違いだと言えます。
高校が4年制の場合、高1がfreshman、高2がsophomore、高3がjunior、高4がseniorになるのは言うまでもありません。米国の場合、kindergartenというのがあり、日本で言うところの幼稚園で、これを小1扱いにして、小学校は5年まで、中学校は6年~8年、高校を9年~12年にしている学区もあるようです。つまり義務教育が13年ということになります。
参考サイトGrade/Grammar/Elementary School 参考サイトfreshman/sophomore/junior/senior